本件はアフィリエイト案件を含みます。
本記事は、「妻のトリセツ」を皮切りに、脳科学の視点からみた「◎◎のトリセツ」シリーズで有名な黒川伊保子さんの著書「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」のレビューです。
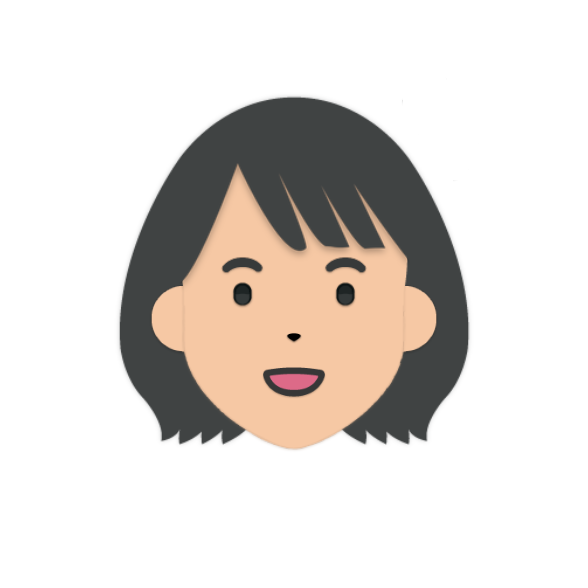
妻のトリセツは、専門的な内容でありながら一般人にもわかりやすく落とし込まれた脳科学の本。
女性ってこうなんだよね!ということを非常にわかりやすく解説してあります。
「息子のトリセツ」「夫のトリセツ」など、シリーズのどの本も面白いですよ。
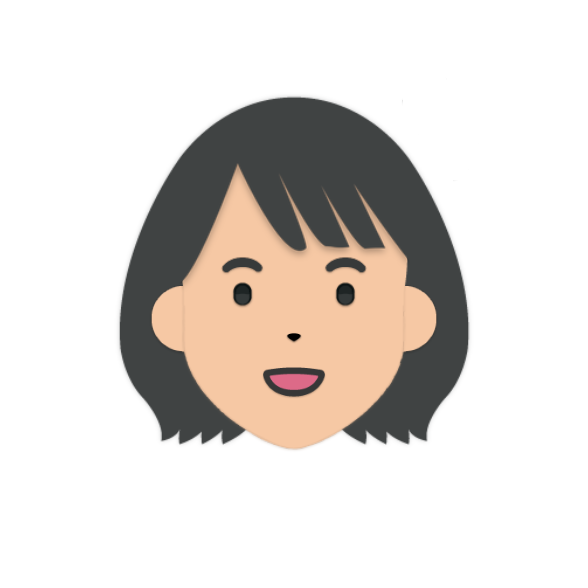
要約するとこんな感じです:
・人工知能研究者としての経験と母親としての実践をもとに、これからのAI時代に適応できる「しあわせ脳」を育てるための指針を示しています。
・好奇心と意欲が旺盛で、穏やかで温かい性格を持ち、集中力や質問力が高い「しあわせ脳」を育てるための具体的な方法が紹介されています。
・その中心となるのが、「早寝、早起き、朝ごはん、適度な運動、そして読書」という基本的な生活習慣を重視する「金のルール」です。
・さらに、AI時代に必要とされる「発想力」や「対話力」を育むために、家庭内での「心理的安全性」の確保が重要であると述べられています。子どもが無邪気に話せる環境を作ることで、発想力や問題解決能力が向上し、AIを使いこなす力が養われます。
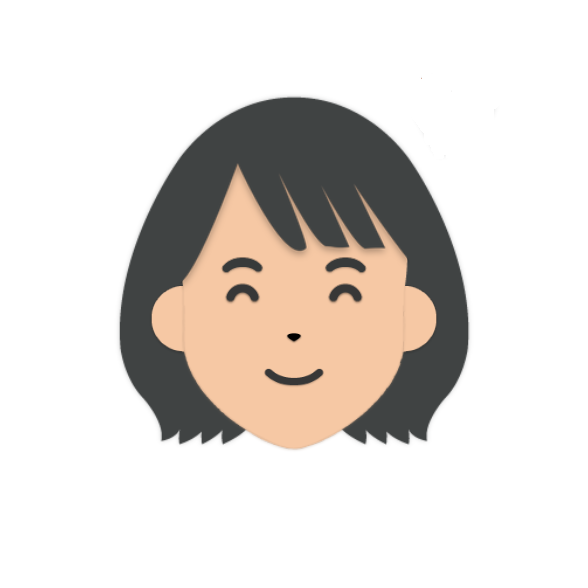
- TOEICスコア975点
- アメリカとカナダの帰国子女
- 社内通訳/翻訳歴20年以上
- 海外ドラマでの英語学習などの情報を発信中。海外ドラマとオンライン英会話で英語力アップを続けています。
Youtubeでの要約も紹介されています。
この本が気になったら、ぜひ自身で手に取って読んでみて下さいね。
情報過多なAI時代の育児の正解を知りたい!という人におすすめしたい一冊です。
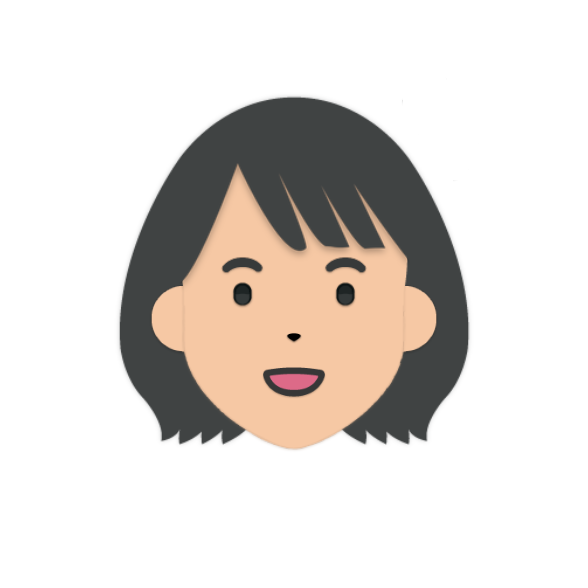
結論からいうと
・早寝早起き朝ご飯、運動、読書
・子供が安心できる環境
があればいい!という内容です。
それではいってみましょう。
- 黒川伊保子先生ってどんな人?「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた
- 黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた
- 黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた「金のルール」とは?
- 黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた:まとめ
黒川伊保子先生ってどんな人?「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた
最初に、黒川伊保子さんとは何者?というところを紹介したいと思います。
黒川伊保子(くろかわ いほこ)さんは、日本の人工知能研究者、随筆家、感性アナリストです。
彼女の本はこんな特徴があります。
専門的な内容なのにわかりやすく、すぐに実践できることを書いてくれているので人気があるのですね。
それでは「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」の大事なポイントをまとめてみたいと思います。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた
この本は大きく以下のパートに分かれています。
- 金のルール
- 銀のルール
- 年齢別、育児するうえで心掛けたいこと
- 黒川さん本人の育児談
「金のルール」とは良い脳を育てるための鉄則「早寝、早起き、朝ご飯、運動、読書」のこと。
「銀のルール」とは子どもの情操にかかわるルールです。
そして、年齢ごとに心がけたいポイントも網羅されています。
ここでは「金のルール」を中心に解説していきたいと思います。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた「金のルール」とは?
黒川先生が考えるいい脳の持ち主とは「幸福の天才」。
頭もいいけど、それ以上に運がいい
という人です。
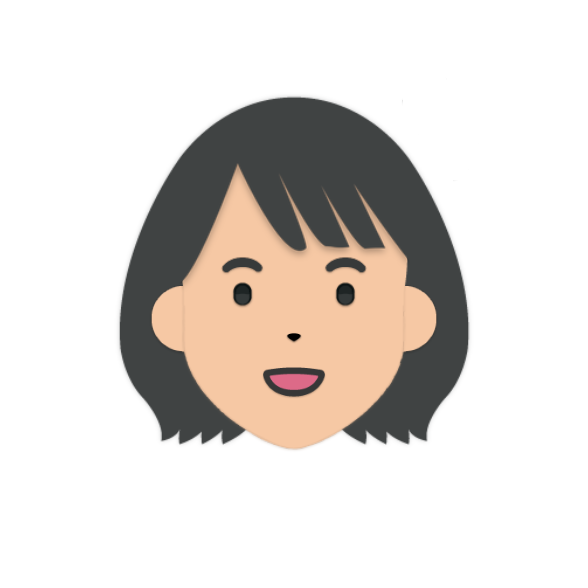
賢さにくわえて、幸せを感じる力が高い人とも言い換えられますね。
そんな黒川先生は一児の母。今は社会人となり、結婚された息子さんがいます。
どんな息子さんなんでしょうか?本によるとこんな人です:
今でも親子仲はとても良いそう。
そんな素敵な息子さんを育てたのが「金のルール」です。
金のルールは「早寝早起き、朝ご飯、運動、読書」!でもどうして?
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた 金のルール①早寝
昔からいわれていることばかりで、何も目新しくないじゃない…と思うかもしれませんが、早寝は脳科学上、とにかく大事とのこと。
なぜなら脳は寝ているあいだに育つから。
脳を正しく育てるには2つのホルモン、「メラトニン」と「セロトニン」をただしく分泌させる必要があります。
メラトニンは眠りのホルモンで、いわばブレーキ役。
セロトニンは別名「幸せホルモン」で、やる気を出してくれる車のアクセルのようなホルモンです。
この2種類のホルモンが正しく分泌されると、脳はすこやかに成長します。
また、子どもは新しく体験することが多く、記憶と認識をつかさどる脳の海馬は大忙しになります。
日中たくわえた、たくさんの経験を整理するのが眠りの役割でもあります。
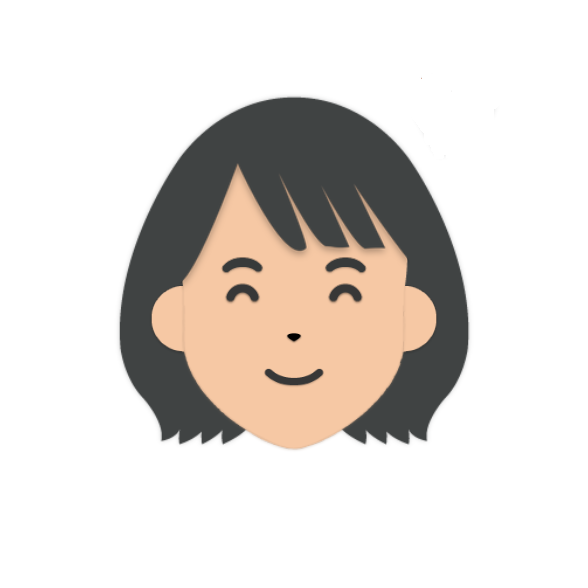
睡眠が大事なのは大人も同じ。アイデアが出ないときは寝たほうがいいそうです。
賢さだけでなく、運動センスも身体も寝ている間に成長します。
理想は10時に寝て6時に起きるサイクル。
よく言われることですが、ブルースクリーンは頭を覚醒させてしまうため、できれば夜9時以降のゲームは控えたほうがよいそう。
そしてお風呂は眠りに入るための最高の方法!と言っています。
ちゃんと湯船に入って体をあたためることが大事なのですね。
それでも眠くなさそうなら、ホットミルクが良いそう。
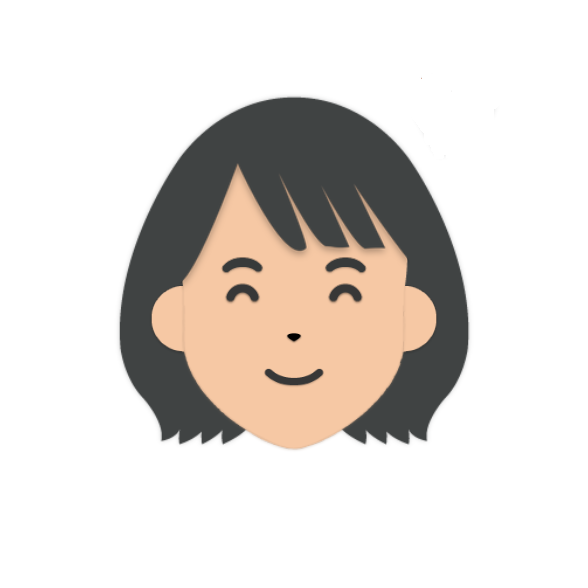
ヨーロッパでは「ナイトミルク」といって、夜中に牛から搾乳したメラトニンたっぷりのミルクを飲む習慣があるのだとか。
それから、6歳以上になったら
「明日何時に起きようか?」
という会話を子どもとするのが良いそうです。
大人もそうですが、起床時間を意識することによって寝覚めがよくなるとのこと。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた 金のルール②早起き
夜たっぷり寝て、朝(できれば6時台に)起きられると脳はセロトニンというホルモンを出すことができます。
これはやる気や幸せな気持ちを感じるホルモンで、さわやかな気持ちにさせてくれます。
朝日を浴びることがとにかく大事です。
早起きできる子どもはキレにくくやる気が持続しやすいそう。
また脳の学習効果も上がるのでいいこと尽くしです。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた 金のルール③朝ごはん
最近はさまざまな理由から朝ごはんを食べずに登園、登校する子もいますが、脳は夜寝ているあいだに頭を整理しているのは前述のとおり。
この作業によって、脳はエネルギーを使い切ってしまっている状態で起床します。
そこに燃料を補給しないのは脳にとって最悪の状態。
朝ごはんはとにかく大事なんです。
菓子パンなど、甘いものの多い朝ごはんはバランスが悪いので、できればバランスのよい朝食を食べましょう。
おかずは多いほうが良いですが、いつもいつも用意するのは親も大変。
時間がないならたまご料理が効率よくバランスのよい食事になるのでおすすめです。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた 金のルール④運動
身体を動かすことも子どもの成長には欠かせません。
運動といってもがっつりスポーツをやらなくては!ということではなく、散歩や汗ばむ程度の家事、自由遊びも運動に含めてOKです。
要は足裏に圧をかけることが大事とのこと。
足裏に圧をかけると、脳からドーパミンとノルアドレナリンというホルモンが出やすくなります。
ドーパミンは好奇心、
ノルアドレナリンは脳のブレーキ役。つまり集中力を高めてくれるホルモンです。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた 金のルール⑤読書
脳に刺激を与えること、つまり体験を増やすのに本はうってつけです。
動画と比べて、読書は主人公に「顔」がありません。
これによって、読書はよりリアルに自分ごととしてインプットされることになります。つまり感情移入しやすいわけですね。
実際に体験しなくても、たとえばファンタジーなどは想像力を育てるのに最高。
想像力だけでなく、ファンタジーの主人公は理不尽な目に遭ったり、世間には悪意というものがあることも教えてくれます。
親が教えることがむずかしいことも、子どもは読書を通じて自然と学んでくれることが可能です。
また、ある程度の年齢になったら、親が子どもに本を与えるよりもおすすめなのは家の本棚から子どもが自分で本を見つけること。
与えられるより、自分で見つけた一冊のほうが読んでいてずっと楽しめます。
それから、親が本を読む姿を見せるのも読書の習慣をつけさせるうえでは大事です。
読書について年齢別のポイント
「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」では、年齢別のおすすめ読書法についても紹介してあります。
0-2歳:ストーリーよりも音感を意識
0-2歳まではストーリーよりも音感を意識できる絵本がおすすめです。
といってもたいていの絵本はそういう造りになっていますよね。
この年齢は、ストーリーというよりも読んでくれる人の姿や声を楽しんでいることが多いので、
「とんとん」「ふわふわ」などの音感を意識して読み聞かせしてあげると喜びます。
また、ことばの発音を学ぶのもこの時期です。
3歳~:少しずつストーリー性のあるものを
3歳からはストーリーを意識した絵本を読んであげましょう。
内容は子どもが自分を投影できるものがおすすめです。
7歳:本人も音読を
ここまではずっと読み聞かせ中心だったかと思いますが、7歳からは音読ができるようになってくるので、子ども自身が音読することも意識しましょう。
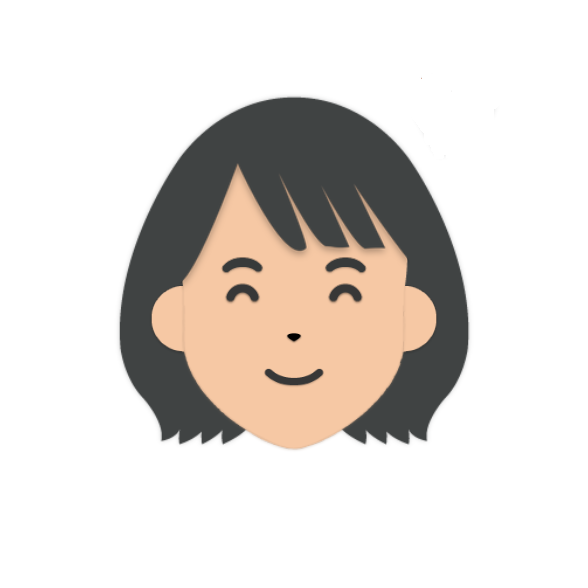
大人と子供が交代で読むのも良さそうですね。
8歳~:読書の一人立ち
脳の言語機能は8歳頃に完成します。
それまでは音を聞きながら頭の中でストーリーを追う必要があり、黙読がまだできない状態でしたが、8歳以上になると親の音読はかえってじゃまになるのでうっとうしがることが増えるはず。
そのため、一人で黙読で読書をできるのがこれぐらいの年齢です。
この年齢におすすめなのはシリーズもの。
実際、ジュニア向けの本はシリーズものが多いですが、これは一度完結したストーリーの主人公が、またちがうストーリーの中で活躍することを子どもが「おもしろい!」と感じるからだそう。
もっと知りたい!という方は「息子のトリセツ」もおすすめです。
時間がない方はイラスト入りバージョンが読みやすいですよ。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた「銀のルール」とは?
「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」では前述の金のルールのほか、「銀のルール」も紹介されています。
銀のルールは子どもの情操にかかわるルールのこと。
言い換えると子どもに安心感を与えて健やかに育てるためのルールです。
おもなポイントは以下の4つです。
銀のルールは「抱っこ、共感、年齢に合った刺激、親の幸せ」!でもどうして?
簡単にまとめましたので、もっと知りたい!という方はぜひ本書を手にとってみてくださいね。
- 泣いたら抱っこする
- 赤ちゃんが泣くのは不安や不快感のサイン。すぐに抱っこして安心させることで、信頼関係が育まれる。
- 感情に共感する
- 「そんなに悲しかったんだね」「怖かったね」と、子どもの気持ちを言葉にして共感すると、安心感が生まれる。
- 子どもの脳の成長に適した刺激を与える
- 乳幼児期は特に、スキンシップや話しかけが脳の発達を促す。過度な刺激や早期教育は逆効果になることも。
- 親の感情の安定が大切
- 親がストレスを抱えていると、子どもにも伝わる。親自身がリラックスすることが、子どもの安心感につながる。
黒川さんは「泣かせっぱなしにしない」「無理に早く自立させようとしない」といった考え方を大切にしています。
これは、赤ちゃんの脳の発達の観点からも理にかなっているとされています。
黒川伊保子先生の「子どもの脳の育て方 AI時代を生き抜く力」を読んでみた:まとめ
終始エッセイ風に書かれており、テンションが高い一冊です(笑)
が、育児するうえで大切なことは脳科学のプロの視点からきっちりとおさえて書いてあります。
育児にかんする情報が多すぎて迷子になりそうな人には
「金のルール」「銀のルール」さえ守っていれば何とかなりそう!
と思わせてくれます。
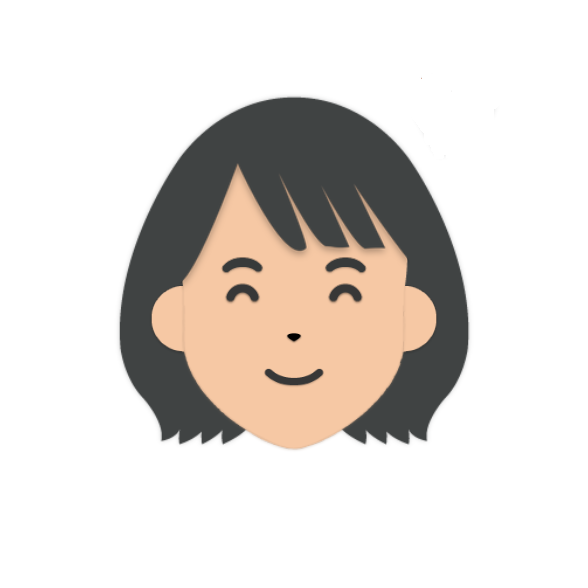
昔から大事とされている「早寝早起き朝ごはん、運動、読書」がなぜ大事かが改めてわかります。
また、黒川さん個人の育児に関するエピソードはとても参考になりますし、ほろりと泣けることも。
改めて育児っておもしろい、育児ができる時間を大事にしたいと思える一冊です!
幼児の英語教育は意味あるの?ということについてもっと知りたいかたは、東進ハイスクールのカリスマ英語教師で有名な関正生先生が子どもの英語教育について真正面から向き合った著書もおすすめです
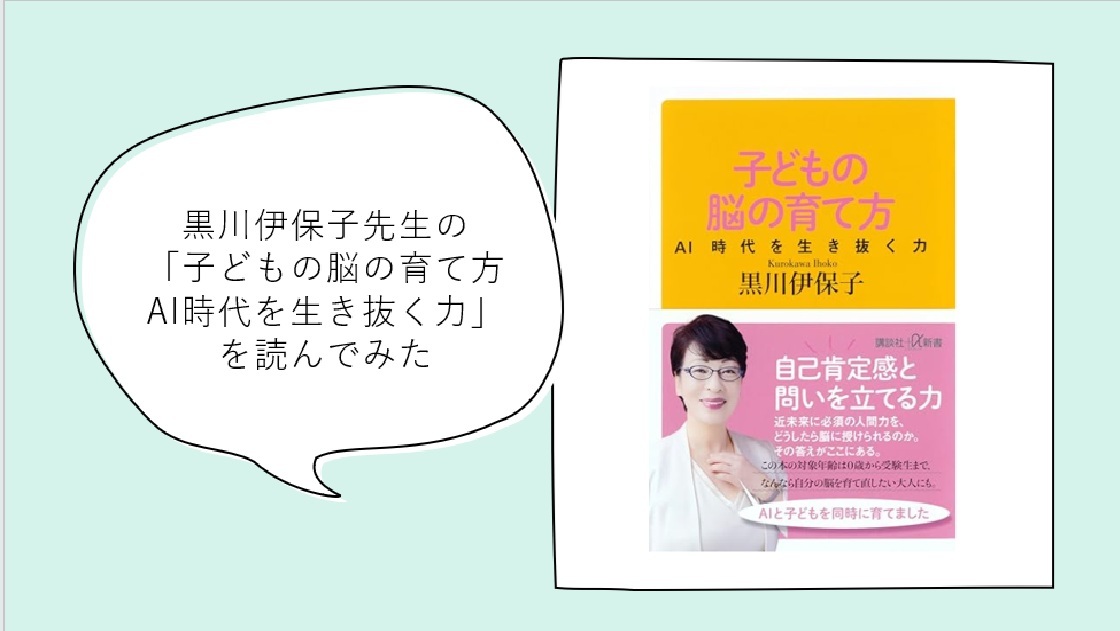



コメント